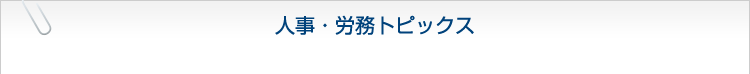2017/12/18
生活保護制度 生活扶助基準の見直しについて議論
厚生労働省は、「社会保障審議会 (生活保護基準部会)」において、「社会保障審議会生活保護基準部会報告書」を取りまとめ、公表しました(平成29年12月14日公表)。
本年は、5年に1度実施される全国消費実態調査のデータ等を用いて、生活扶助基準の検証を行う年に当たることから、生活扶助基準が最低生活保障として適切な水準となっているか否かなどの検証が行われ、その結果などが取りまとめられています。
たとえば、モデル世帯、夫婦子一人世帯については、一般低所得世帯の消費支出額と生活扶助基準額は概ね均衡していますが、他方で、生活扶助基準額は、年齢と世帯人員数と地域の3つの要素を考慮して金額を決めることになっており、この要素を消費の実態に合わせると、世帯類型や居住地によって個々の世帯の生活扶助費の金額と実態の金額についていろいろばらつきがあるということが報告されています。
政府は、この報告書を踏まえて、来年度以降の生活扶助基準を決定していくことになるわけですが、委員からも、検証結果をそのまま反映すると大変影響が大きくなるという意見があったようです。
加藤厚生労働大臣は、こういったことを踏まえて、「それぞれの世帯、地域、世帯人員といったことを細かく見ながら、しっかり影響に十分目配りをして、最終的な姿、案を固めていきたいと思います。」とコメントしています。
なお、検証結果のみを考慮すると、生活扶助の引き下げ率は、最大で14%にもなるということで、生活保護の受給者や弁護士などが厚生労働大臣に抗議文を提出したという一幕もあったようです。
一部報道では、「生活扶助の引き下げ率を最大で5%に抑える方針を固めた」などと報じています。
具体的に、どのような見直しが行われるのか、注目です。
報告書については、こちらをご覧ください。
<社会保障審議会生活保護基準部会報告書>
« 改正民法 施行日は平成32年(2020年)4月1日に決定 | 平成30年版の源泉徴収のしかたを掲載(国税庁) »
記事一覧
- 厚生労働大臣会見概要 基礎年金の底上げを年金制度改革関連法案から削除したことなどについて質疑応答(令和7年4月18日) [2025/04/21]
- 「採用力をあげるテレワーク」(テレワーク総合ポータルサイトのコラム) [2025/04/21]
- 「地域経済の好循環を支える中小企業・小規模事業者の「稼ぐ力」の強化に向けて」を公表(日商) [2025/04/21]
- 日本年金機構からのお知らせ 「短時間労働者の適用拡大<被保険者資格取得届の届出漏れはありませんか>」などの情報を掲載 [2025/04/18]
- 1,000円着服で退職金1,200万円を全額不支給 最高裁の判断は適法 [2025/04/18]