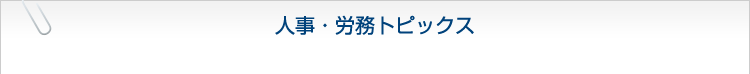2018/09/19
裁量労働制で労基署が是正勧告 不適切な労使協定
「東京都内のある建築設計事務所が、専門業務型の裁量労働制を導入するための労使協定を適切に締結していなかったなどとして、中央労働基準監督署(東京)から、当該裁量労働制の適用は無効と指導され、是正勧告を受けていたことが分かった。」といった報道がありました(是正勧告は、平成30年9月6日付)。
同月18日に、その裁量労働制の対象となっていた労働者とこれを支援する労働組合が記者会見を開き明らかにしたものです。
労働者側によると、その労働者は、みなし労働時間を1日8時間とする専門業務型の裁量労働制を適用され、残業が月80時間を超えることが大半だったということです。
専門業務型の裁量労働制を導入するためには、会社側が、労働組合か労働者の過半数に多数決などで選ばれた労働者(労働者の過半数を代表する者)と、労使協定を結ぶ必要がありますが、同社は、会社が指名した者を労働者側の代表者として労使協定を結んでいたようです。
労働基準監督署は、この協定に基づく同制度の適用を無効と判断。
労働者に違法な残業をさせ、残業代を支払わなかったとして、是正勧告をしました。
その労働者の未払い残業代は、過去2年間で約700万円で、同社には同じ労使協定で裁量労働制を適用された社員が約80人いるということです。
労働基準法には、労使協定を導入要件とする制度がいくつかありますが、その前提となる労使協定の締結相手を適切に選出する必要がありますね。
【確認】 労使協定(36協定もその一種です)は、使用者(会社)が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは「労働者の過半数を代表する者」と締結する必要があります。
今回、問題となったのは、「労働者の過半数を代表する者」で、これが会社が指名した者だったということです。
従来から、その選出方法は、厚生労働省令(労働基準法施行規則)に規定されていましたが、この度の働き方改革関連法による改正の一環で、次のような改正が行われます(施行は、平成31(2019)年4月1日)。
●労働者の過半数を代表する者は、労使協定をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であって、『使用者の意向に基づき選出されたものでないこと』(『 』のような要件を追加)
省令にも明記されましたので、くれぐれも、使用者(会社)の意向を持ち込まないようにして選出するようにしましょう。
〔参考〕省令改正条文(平成30年9月7日公布))
https://www.mhlw.go.jp/content/000350655.pdf
※興味があれば、労働基準法施行規則の第6条の2(1項2号)の改正規定をご覧ください。
« 平成31年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書 順次送付を開始(日本年金機構) | 働き方改革関連法で労働基準法などの改正に関する通達を公表 »
記事一覧
- 日本年金機構からのお知らせ 「短時間労働者の適用拡大<被保険者資格取得届の届出漏れはありませんか>」などの情報を掲載 [2025/04/18]
- 1,000円着服で退職金1,200万円を全額不支給 最高裁の判断は適法 [2025/04/18]
- 令和7年春闘 第4回回答集計 賃上げ率5.37%(中小4.97%)で昨年同時期を上回る(連合) [2025/04/18]
- 中小企業4団体連名で「最低賃金に関する要望」をとりまとめ(日商など) [2025/04/18]
- 基礎控除等の引上げと基礎控除の上乗せ特例の創設(財務省が資料を公表) [2025/04/17]