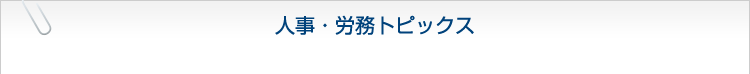2022/07/19
「これからの労働時間制度に関する検討会」の報告書を公表(厚労省)
裁量労働制実態調査において把握した実態等を踏まえ、裁量労働制その他の労働時間制度について検討を行うため、厚生労働省では「これからの労働時間制度に関する検討会」において検討を重ねてきました。
令和4年7月15日、この検討会の報告書が取りまとめられ、公表されました。
報告書によると、これからの労働時間制度に関する基本的な考え方については、次のとおりとされています。
□ 現在の労働時間法制が労使のニーズや社会的要請に適切に対応し得ているのかは、常に検証を行っていくことが必要
□ 労使のニーズに沿った働き方は、これまでに整備されてきた様々な制度の趣旨を正しく理解した上で制度を選択し、運用することで相当程度実現可能
まずは各種労働時間制度の趣旨の理解を労使に浸透させることが必要
□ その上で、これからの労働時間制度は、次の視点に立って考えることが必要
・どのような労働時間制度を採用するにしても、労働者の健康確保が確実に行われることを土台としていくこと
・労使双方の多様なニーズに応じた働き方を実現できるようにすること
・労使当事者が十分に協議した上で、その企業や職場、職務内容にふさわしい制度を選択、運用できるようにすること
今後、働き方改革関連法(2019年4月施行)の施行5年後の検討が行われることになりますが、これに加えて、労働時間法制について、経済社会の大きな変化を十分に認識し、将来を見据えた検討を行っていくことが求められるとしています。
その検討に当たっては、この報告書の基本的な考え方を踏まえるとともに、特に次の課題や視点について議論を深めていくことが必要としています。
□ 現行制度を横断的な視点で見直し、労使双方にとって分かりやすいものにしていく
□ IT技術の活用などによる健康確保の在り方、労働者自身が行う健康管理を支援する方策等について検討
□ 労働時間制度等に関する企業による情報発信を更に進めていく
□ 各企業の実情に応じて労働者の意見が適切に反映される形でのコミュニケーションが重要。過半数代表制や、労使委員会の在り方も課題。適切な労使協議の場の制度的担保を前提として、労使協議により制度の具体的内容の決定を認める手法も検討課題
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「これからの労働時間制度に関する検討会」の報告書を公表します>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26843.html
« 化学物質管理に関する社内安全衛生教育用eラーニング教材を公表(厚労省) | 基本的対処方針の変更や効果的な換気方法の周知などについて 経団連からお知らせ »
記事一覧
- 令和7年度の地方労働行政運営方針 最低賃金・賃金の引上げに向けた支援、非正規雇用労働者への支援、リ・スキリング、ジョブ型人事(職務給)の導入などが示される(厚労省) [2025/04/03]
- 令和7年4月分からの年金額等についてお知らせ 在職老齢年金の計算方法も確認しておきましょう(日本年金機構) [2025/04/03]
- 経営改善計画策定支援・早期経営改善計画策定支援についてマニュアル・FAQなどを改定(中小企業庁) [2025/04/03]
- 令和7年度の雇用・労働分野の助成金 全体のパンフレット簡略版などを公表(厚労省) [2025/04/02]
- 雇用保険に関する業務取扱要領(令和7年4月1日以降)を公表 [2025/04/02]