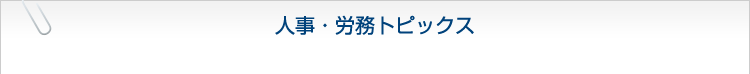2022/12/08
メリット制の適用を受ける事業主が労働保険料認定決定に不服を持つ場合の対応 報告書案を提示(厚労省の検討会)
厚生労働省から、令和4年12月7日開催の「第2回 労働保険徴収法第12条第3項の適用事業主の不服の取扱いに関する検討会」の資料が公表されました。
この検討会の設置の背景・検討事項は、次のとおりです。
- 労災保険給付支給決定がなされた場合、メリット制適用事業主は、労働保険料の負担が増大する可能性がある。
しかしながら、メリット制適用事業主は、⑴労災保険給付支給決定に関する争いの当事者となる資格がないこととされている(メリット制適用事業主の労災保険給付支給決定に対する審査請求適格を否定)。
また、⑵労働保険料認定決定の適否を争う際に、労災保険給付支給決定の要件該当性に関する主張はできないこととされている(労働保険料認定決定において労災保険給付支給決定の要件該当性に関して主張することを否定)。
- 仮に⑴が肯定されると、被災労働者等と利害が相反する事業主により争訟が提起され、被災労働者等の法的地位が不安定になることなどが考えられる。
- 仮に⑵が肯定されると、被災労働者等に保険給付が既にされた後に当該給付の根拠を失わせる可能性が生じ、被災労働者等の法的な地位の安定性の観点から問題があることが考えられる。
そこで、この検討会において、その対応を検討することとされました。
2回目となる今回の検討会では。報告書案が提示されています。
その報告書案の「まとめ」のなかで、厚生労働省は、3点を含めた必要な措置を講じることが適当であるとしています。
①保険料認定処分の不服申立等において、労災支給処分の支給要件非該当性に関する主張を認める。
②保険料認定処分の不服申立等において労災支給処分の支給要件非該当性が認められた場合には、その労災支給処分が労働保険料に影響しないよう、労働保険料を再決定するなど必要な対応を行う。
③保険料認定処分の不服申立等において労災支給処分の支給要件非該当性が認められたとしても、そのことを理由に労災支給処分を取り消すことはしない。
複雑な内容となりそうですが、今後の動向に注目です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<第2回「労働保険徴収法第12条第3項の適用事業主の不服の取扱いに関する検討会」/資料>
« 全世代型社会保障の構築に向けた各分野における改革の方向性を示す(全世代型社会保障構築会議) | 職業生活に関してストレスを感じている労働者は74.3% 要因の1位は「職場の人間関係」(連合の調査) »
記事一覧
- 日本年金機構からのお知らせ 「短時間労働者の適用拡大<被保険者資格取得届の届出漏れはありませんか>」などの情報を掲載 [2025/04/18]
- 1,000円着服で退職金1,200万円を全額不支給 最高裁の判断は適法 [2025/04/18]
- 令和7年春闘 第4回回答集計 賃上げ率5.37%(中小4.97%)で昨年同時期を上回る(連合) [2025/04/18]
- 中小企業4団体連名で「最低賃金に関する要望」をとりまとめ(日商など) [2025/04/18]
- 基礎控除等の引上げと基礎控除の上乗せ特例の創設(財務省が資料を公表) [2025/04/17]