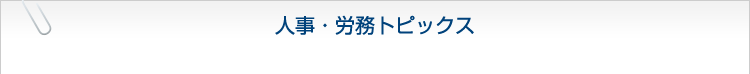コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2018/02/06
賃金等の請求権の消滅時効 延長? 現状維持?(第2回検討会)
厚生労働省から、平成30年2月5日に開催された「第2回賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会」の資料が公表されました。
労働基準法第115条における賃金等請求権の消滅時効の期間は2年とされていますが、平成32年(2020年)4月から、民法の一部改正により、賃金を含む一般債権の消滅時効の期間について、複数あった時効の期間が統一され、「知った時から5年(権利を行使することができる時から10年の間に限ります)」とされることになりました。
これに伴い、労働基準法に規定する賃金等請求権の消滅時効の期間をどうするか? ということで行われている検討です。
今回の第2回目の検討会では、法曹関係者からのヒアリングなどが行われました。
具体的には、労働者側と使用者側の双方の考え方について複数の弁護士が意見を述べたとのことです。
労働者側は民法に合わせて時効延長、使用者側は現行の労働基準法上の時効の維持を、それぞれ主張する構図になっています。
なお、現行の労働基準法第115条では、「賃金(退職手当を除く)、災害補償その他の請求権は2年」、「退職手当の請求権は5年」の消滅時効が定められていますが、ここでいう”その他”の請求権には、年次有給休暇の請求権も含むこととされています。
そのため、年次有給休暇の請求権の時効をどうするか? といった論点も生じています。
仮に、年休の時効の期間が5年となり、年休が5年前の分まで繰り越されるとすると、労働者は、理論上は、最大で1年度に100日の年休の権利を行使できることになります。100日は極端な例ですが、毎年度5日の未消化分がある例で考えても、「その年度の年休の日数+20日(5日×4年分)」の年休の権利を行使できることになり、企業にとって大きな負担になることは間違いありません。もしそうなった場合、年休の消化率が低ければ、退職前にまとめて年休を消化する期間も長くなることになりますね。
その他、時効の期間の起算点や書類の保存期間との関係なども論点となっています。
今後も幾度か検討を重ね、平成30年夏を目途に検討結果の取りまとめが行われることになっています。動向に注目です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
特に、資料3の意見と資料4の意見を比較すると、この検討の意味が見えてくると思います。
<第2回賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会/資料>
≫ http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000193254.html
« 労働保険特別会計の平成30年度の予算の概要を公表 | 障害者雇用対策基本方針の改正について議論 »
記事一覧
- 厚生労働大臣会見概要 基礎年金の底上げを年金制度改革関連法案から削除したことなどについて質疑応答(令和7年4月18日) [2025/04/21]
- 「採用力をあげるテレワーク」(テレワーク総合ポータルサイトのコラム) [2025/04/21]
- 「地域経済の好循環を支える中小企業・小規模事業者の「稼ぐ力」の強化に向けて」を公表(日商) [2025/04/21]
- 日本年金機構からのお知らせ 「短時間労働者の適用拡大<被保険者資格取得届の届出漏れはありませんか>」などの情報を掲載 [2025/04/18]
- 1,000円着服で退職金1,200万円を全額不支給 最高裁の判断は適法 [2025/04/18]