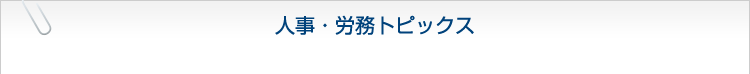コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2019/05/23
「高齢社会における資産形成・管理」報告書(案)を提示(金融審議会のWG)
令和元年(2019年)5月22日に開催された「金融審議会『市場ワーキング・グループ』(第23回)」において、「『高齢社会における資産形成・管理』報告書(案)」が提示され、ちょっとした話題になっています。
これは、人生100年時代に向け、長い老後を暮らせる蓄えにあたる「資産寿命」をどう延ばすかという問題などについてまとめられたものです。
働き盛りの現役期、定年退職前後、高齢期の3つの時期ごとに、資産寿命の延ばし方の心構えが示されています。
報告書(案)では、「公的年金の水準については、中長期的に実質的な低下が見込まれているとともに、税・保険料の負担も年々増加しており、少子高齢化を踏まえると、今後もこの傾向は一層強まることが見込まれる」と指摘しています。
さらに、具体的な内容にも触れ、年金だけが収入の無職高齢夫婦(夫65歳以上、妻60歳以上)だと、家計収支は平均で毎月約5万円の赤字。蓄えを取り崩しながら20~30年生きるとすれば、現状でも1,300万円~2,000万円が必要に
なり、長寿化で、こうした蓄えはもっと必要になるとしています。
その上で、現役期は「少額からでも資産形成の行動を起こす時期」とし、生活資金を預貯金で確保しつつ、長期・分散・積み立て投資が必要としています。
具体的な方法としては、「つみたてNISA」や、個人型の確定拠出年金「iDeCo(イデコ)」などがあげられています。
このような内容であることから、「政府が年金など公助の限界を認め、国民の『自助』を呼びかける内容になっている。」などといった報道もされています。
正式に決定され、公表されたら、さらに話題になるかもしれませんね。
まだ、案の段階ですが、詳しくは、こちらをご覧ください。
<金融審議会「市場ワーキング・グループ」(第23回)/資料>
https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/market_wg/siryou/20190522.html
※報告書(案)については、「資料1」参照。
« シェアード会社の勤務社労士の業務の範囲などについてヒアリング(規制改革推進会議の部会) | 年休の時季指定義務について新たなリーフレットを公表(厚労省) »
記事一覧
- 令和7年度の労働保険の年度更新期間などについてお知らせ(厚労省) [2025/04/04]
- 賃金のデジタル払い 資金移動業者を厚生労働大臣が指定 これで4社目(厚労省) [2025/04/04]
- 令和7年春闘 第3回回答集計 賃上げ率5.42%(中小5.00%)で昨年同時期を上回る(連合) [2025/04/04]
- 不妊治療と仕事との両立 マニュアル等を公表(厚労省) [2025/04/04]
- 労働者協同組合の設立状況 施行後施行後2年6か月で計144法人の設立(厚労省) [2025/04/04]