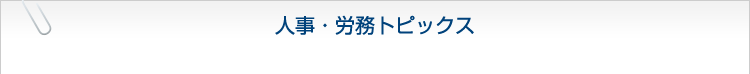コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2019/06/14
賃金等請求権の消滅時効の在り方 現行の2年から延長する方向か(検討会での論点整理)
厚生労働省から、「第9回賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会」の資料が公表されました(令和元年(2019年)6月13日公表)。
労働基準法第115条における賃金等請求権の消滅時効の期間は2年とされていますが、令和2年(2020年)4月から、民法の一部改正により、賃金を含む一般債権の消滅時効の期間について、複数あった時効の期間が統一され、「知った時から5年(権利を行使することができる時から10年の間に限ります。)」とされることになりました。
これに伴い、労働基準法に規定する賃金等請求権の消滅時効の期間をどうするか?ということで行われているのが、この検討会での議論です。
今回、『「賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会」論点の整理(案)』が公表されています。
その中で、「労働者の権利を拡充する方向で一定の見直しが必要ではないか」という考えが示されています。
具体的には、次のとおりです。
●賃金請求権の消滅時効期間について
・労基法第115条の消滅時効期間については、労基法制定時に、民法の短期消滅時効の1年では労働者保護に欠けること等を踏まえて2年とした経緯があるが、今回の民法改正により短期消滅時効が廃止されたことで、改めてその合理性を検証する必要があること
・現行の2年間の消滅時効期間の下では、未払賃金を請求したくてもできないまま2年間の消滅時効期間が経過して債権が消滅してしまっている事例などの現実の問題等もあると考えられること
・仮に消滅時効期間が延長されれば、労務管理等の企業実務も変わらざるを得ず、紛争の抑制に資するため、指揮命令や労働時間管理の方法について望ましい企業行動を促す可能性があること
などを踏まえると、仮に上記の賃金請求権の特殊性を踏まえたとしても、現行の労基法上の賃金請求権の消滅時効期間を将来にわたり2年のまま維持する合理性は乏しく、労働者の権利を拡充する方向で一定の見直しが必要ではないかと考えられる。
●賃金請求権以外の消滅時効
現行の労基法上、賃金請求権以外の請求権については、賃金請求権と同様に2年と設定されており、基本的には賃金請求権の消滅時効の結論に合わせて措置を講ずることが適当と考えられる。
しかしながら、年次有給休暇と災害補償については、特に留意が必要であり、これを踏まえて速やかに労働政策審議会で検討することが適当である。
今夏以降、労働政策審議会において、5年を軸に消滅時効の期間の延長年数などが議論されることになりそうです。
本格的な議論はこれからですが、労基法上の消滅時効の期間が延長されるとなれば、企業実務に及ぼす影響は非常に大きいです。
動向に注目です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<第9回賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000211189_00013.html
« 災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等に係る許可基準を一部改正(厚労省) | 障害者雇用促進法の一部改正が公布 短時間であれば就労可能な障害者等の雇用機会確保を支援する制度も創設 »
記事一覧
- 令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について 国税庁が専用ページを設け各種情報を掲載 [2025/04/28]
- 第96回メーデー中央大会 石破総理も出席 「2020年代に最低賃金の全国平均1,500円」「人財尊重社会」の実現に向けて今後とも最大限の努力をする [2025/04/28]
- 2025年版 中小企業白書・小規模企業白書を公表(中小企業庁・経産省) [2025/04/28]
- 就職氷河期世代の支援強化へ 関係閣僚会議が初会合 [2025/04/25]
- 労政審の労働政策基本部会が報告書をとりまとめ 地方や中小企業での良質な雇用の在り方がテーマ [2025/04/25]