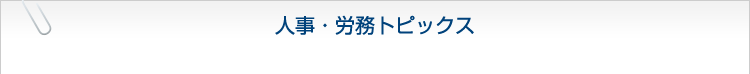2024/11/13
世帯主が65歳以上の世帯 2050年には21県で世帯総数の50%以上に(国立社会保障・人口問題研究所)
・11月12日
国立社会保障・人口問題研究所から、「日本の世帯数の将来推計(都道府県別推計)-令和6(2024)年推計-」が公表されました(令和6年11月12日公表)。
この推計は5年ごとに実施されており、世帯の家族類型別にみた将来の世帯数を都道府県別に求めることを目的としています。
今回は、令和2(2020)年の国勢調査を基に、令和32(2050)年までの30年間について将来推計が行われています。特に、次のような推計結果が注目されています。
●2050年には、半数近い都道府県で50%以上の世帯が、世帯主が65歳以上の世帯。3分の2の都道府県で、5世帯に1世帯が65歳以上の単独世帯に
・都道府県の世帯総数のうち世帯主が65歳以上の世帯が占める割合は、2050年には21県で50%を超え、秋田では60%を超える。65歳以上の単独世帯の割合は、2050年に32道府県で20%を超える。
・65歳以上の人のうち単独世帯である割合(独居率)もすべての都道府県で上昇し、2050年には山形以外で20%を超え、5都府県では30%を超える。
●4県では、2050年の75歳以上の単独世帯の数が2020年の2倍以上に
・人口の動向を背景に、都道府県でも、世帯主が75歳以上の世帯の数は2030年頃と2050年に二度のピークを迎え、すべての都道府県で2050年の世帯数は2020年より多くなる。
また、2050年の75歳以上の単独世帯の数もすべての都道府県で2020年より多く、4県(沖縄、滋賀、埼玉、茨城)では2倍以上になる。
・75歳以上の人のうち単独世帯である割合(独居率)もすべての都道府県で上昇し、2050年には山形以外で20%を超え、8都府県では30%を超える。
このような将来推計をみると、高齢者が一人暮らしでも安心できるような支援態勢を構築することが急務と言えそうです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<日本の世帯数の将来推計(都道府県別推計)(令和6(2024)年推計)の結果を公表しました。
https://www.ipss.go.jp/pp-pjsetai/j/hpjp2024/t-page.asp
« デジタル行財政改革の今後の取組方針について議論(デジタル行財政改革会議) | 今後の規制・制度改革の検討課題 「年収の壁」支援強化パッケージの手続き円滑化、最低賃金の決定プロセスの見直し、副業... »
記事一覧
- 就職氷河期世代の支援強化へ 関係閣僚会議が初会合 [2025/04/25]
- 労政審の労働政策基本部会が報告書をとりまとめ 地方や中小企業での良質な雇用の在り方がテーマ [2025/04/25]
- 時間外・休日労働協定届の本社一括届出などについて新たな通達を公表(厚労省) [2025/04/25]
- 「『多様な正社員』制度導入マニュアル」を公表(多様な働き方の実現応援サイト) [2025/04/25]
- 財政制度分科会 持続可能な社会保障制度の構築について議論 財政面からみた論点を整理(財務省) [2025/04/25]